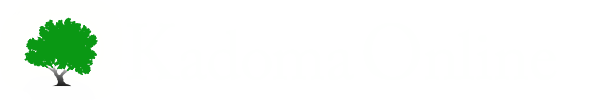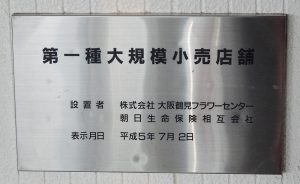日本における“アウトレットの元祖”として知られる門真南駅近くの「三井アウトレットパーク大阪鶴見」(鶴見区茨田大宮)が来年2023年3月12日で閉店し、松生町のパナソニック工場跡(南門真地区)の再開発地へ拡張移転することが決まりました。
三井アウトレットパーク大阪鶴見が営業している建物「鶴見はなぽ~とブロッサム」の土地は大阪市が所有しており、契約期限が今年度末の2023年3月に迫っているなかでの移転となります。
鶴見はなぽ~とブロッサムは、花の市場「大阪鶴見花き卸売市場」(1994年7月開場)と三井不動産によるアウトレットパーク(1995年3月開業)の複合施設。
鶴見緑地で行われた「花博(国際花と緑の博覧会)」(1990年4月~9月)の成功を受け、地下1階から地上2階を卸売市場とし、3階から5階は花に関する交流施設という位置付けで、府と市などが出資する第三セクター「株式会社大阪鶴見フラワーセンター」と朝日生命が共同で建設したものでした。
建物は地下1階から地上2階部分を大阪鶴見フラワーセンター、3階から5階部分は朝日生命がそれぞれ所有する形となっており、朝日生命が三井不動産に転貸する形でアウトレットが運営されています。
約2万6000平方メートルの土地は、1970年代から大阪市が所有しており、花博開催時には駐車場として活用していました。
大阪市が花の卸売市場を運営する大阪鶴見フラワーセンターに土地を貸し付けており、朝日生命は3階から5階部分の土地の使用料分(転貸借契約分)を支払うという形になっています。
2023年3月末に迫っていた借地期限
この鶴見はなぽ~とブロッサムには、“登場人物”が多く複雑なので整理すると、次のような枠組みで運営されています。
- 土地所有:大阪市
- 土地借用:株式会社大阪鶴見フラワーセンター(府と市の第三セクターで花の卸売市場運営者)
- 建物所有:株式会社大阪鶴見フラワーセンター(地下1階~地上2階部分)/朝日生命保険相互会社(3階~5階部分)
- 建物使用:大阪鶴見花き卸売市場(地下1階~地上2階部分、関係会社・施設などを含む)/三井アウトレットパーク大阪鶴見(3階~5階部分)
つまり、鶴見はなぽ~とブロッサムの“影のオーナー”は大阪市ではあるものの、建物や運営については全面的に関与せず、という格好です。
大阪市や府が議会で説明したところでは、現在の借地契約は2023年3月末(2022年度末)までだといいます。
アウトレット部分を運営する三井不動産としては、土地の契約期限を迎える来年3月末までに撤退を決断することになりました。
花博とバブルの名残りを反映した建物
複雑な枠組みで運営されている鶴見はなぽ~とブロッサムですが、建設された経緯を振り返ってみると、次のような歩みをたどってきました。
▼ 1970年代
- 田畑だった茨田大宮周辺の土地を大阪市が買い続ける(中央環状線沿いの将来開発のためか?花博時には駐車場として有効活用)
▼ 1990(平成2)年
- 鶴見緑地で「花博」が大成功。これを受け、“花博メモリアル”の一つとして花の卸売市場の誘致機運が高まる
- 時はバブル経済、せっかくだから卸売市場だけでなく、一般の人も楽しめる施設にしようとの意見
- 大阪市としては市民の財産である土地を売ることはできないが、卸売市場だけだと早朝しか使われないため、昼間に人が集まる“交流施設”を設けるのは「いいことだ」といった認識
- 市は土地を貸すが、卸売市場は第三セクター、交流施設は民間にやってもらいたいとの考え
▼ 1991(平成3)年
- 建物のコンペを行い、説明会には民間企業8社が参加するなど注目を集めたが、バブル景気後退の局面もあって、結局コンペに応募したのは朝日生命(背後に三井不動産がいたのかどうかは不明)しかいなかったという
- 開閉式の花びら状の可動式屋根「ブロッサムウィング」や、地上95メートルの「アトリウムタワー」と「スカイバルーン」(展望観覧車)を設置するといった形の施設が設計される
▼ 1992年~94年ごろ
- アウトレットを運営する三井不動産によると、「日本での前例がなかったため、テナント誘致などに苦戦しましたが、工場からの直接仕入れによって人気ブランド商品を手ごろな価格で販売するという手法は注目を集め、今では日本全国に三井アウトレットパークを展開するまでに拡がりました」(同社「沿革」より)という
- なお、テナントの誘致に苦労した背景として、当時はバブル経済崩壊の兆しが見られた影響を指摘する声もある
▼ 1994(平成6)年7月
- 建物の地下1階~地上2階に「大阪鶴見花き卸売市場」がオープン
▼ 1995(平成7)年3月
- 鶴見はなぽ~とブロッサムの交流施設(アウトレット・展望塔)部分(3階~5階)がオープンし、施設が全面開業
- 開店時は51店舗でスタートし、アウトレット店舗は「ナイキ」や「リーボック」、「エディーバウアー」など41店。その他、スヌーピーグッズ専門店やカフェ、ギャラリーからなるテーマハウス「スヌーピータウン」(2006年閉店)、展望観覧車「スカイバルーン」(現在休止)などが注目を集める
▼ 1997年(平成9年)8月
- 近くに長堀鶴見緑地線の「門真南」駅が開業。「なみはやドーム」も建設され、「なみはや国体」のメイン会場となる
▼ 2008(平成20)年4月
- 三井不動産は、全国で運営するアウトレットパークの名称を「三井アウトレットパーク」+「地域名称」に変更・統一し、鶴見はなぽ~とブロッサムも「三井アウトレットパーク大阪鶴見」に変える
▼ 2021(令和3)年10月
- 三井不動産が松生町にあったパナソニックの工場跡地(南門真地区)の再開発「(仮称)門真市松生町商業施設計画」への参入を発表
▼ 2022(令和4)年7月(今月)
- 門真市松生町商業施設計画では「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」の複合型商業施設として2023年春に開業すること、現在の「三井アウトレットパーク大阪鶴見」は2023年3月限りで閉店することを発表

松生町のパナソニック跡地で2023年春にオープンを予定する「三井ショッピングパーク ららぽーと」(1・3階=約150店舗)「三井アウトレットパーク」(2階=約100店舗)複合型商業施設の完成予想図(三井不動産のニュースリリースより)
▼ 2023(令和5)年3月末(予定)
- 大阪市と株式会社大阪鶴見フラワーセンターの土地貸借の契約期限を迎える(市場部分は更新となる見通し)
以上のように、その経緯を見ると、鶴見はなぽ~とブロッサムは、1990年代初頭まで続いた「バブル経済」の名残りを色濃く残した“官製施設”との見方ができます。
開業した頃には、「花の卸売市場とアウトレットは何の関係性もないやないか、どちらも中途半端ではないか」との声もありましたが、日本でまだ珍しかったアウトレットモールは人気を集めました。
また、アウトレットモールとしては、現在まで拡大を続ける業態を日本に確立するきっかけとなった施設として、その功績は小さくなく、今も一定の集客力を保ちます。
ただ、現在では三井不動産が運営するアウトレットは大型化が進んでおり、大阪鶴見(約70店舗・2019年の売上78億円)の規模は最小クラスとなっています。
建物の老朽化も進むなか、土地の契約期限を迎えるのを機に重要なテナントである三井不動産が逃げた、とも見えますし、近くの松生町の再開発に参入したことで、2つの大型商業施設を運営していく体力がなかったとも考えられます。
一方、「卸売市場」として見ると、近年は取扱量の拡大が続いていたため、「施設が狭い」という課題も出ていたといいます。
アウトレットが出ていった後に卸売市場のスペースを拡大すれば丸く収まるのかもしれませんが、テナント使用料分の収入が入らないとなると、今では用途がほぼなくなった「高い塔」や「可動式屋根」を含む建物の維持管理費用は頭の痛いところです。そうした不要な設備を除去するにしても費用がかかってしまいます。
今後、アウトレット部分の建物を所有する朝日生命がどのような決断を下すのでしょうか。また、実質的な“大家”である大阪市は、一部を商業施設として使うことを主導してきた経緯があるだけに、建物の適切な管理と卸売市場の継続という面で、支援や関与していく必要にも迫られそうです。
門真南駅前「門真の市有地」にも注目
門真市民の視点では、門真南駅近くの「三井アウトレットパーク大阪鶴見」が閉店した後も、松生町に拡大移転するため、ほとんど影響がないとも言えますし、逆に市内へ移ってくるので喜ばしいことでしょう。大阪モノレールの延伸時には松生町に新駅も設けられます。
ただ、門真南駅の賑わいという視点で見ると、今後は朝日生命が三井アウトレットパークの跡地を商業施設として活用しないならば、駅周辺での重要な集客施設を失ってしまうことになります。
そこでもう一つ、動向を注目しておきたいのは門真南駅の駅前で2019(平成31)年3月に閉鎖された「門真市浄化センター」の跡地です。
いわゆる“汚物処理場(し尿処理場)”として1962(昭和37)年に建てられた施設ですが、今では市内に下水道が普及し、四條畷市の施設で処理してもらえるようになったことから廃止されました。
鶴見はなぽ~とブロッサムの敷地と比べ、こちらは三分の一規模の面積にとどまりますが、駅の目の前という場所に約8500平方メートルという門真市の未利用地が現れることになります。
現時点で門真市当局は、土地を売却する方針に傾いているようですが、門真南駅の賑わいや集客につながる土地活用を望みたいところです。
(2022年7月9日時点の内容です)