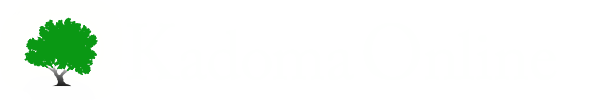大和田駅前の再生へ向けて一歩を踏み出します。門真市内では古川橋駅前のタワーマンション・新図書館建設、門真市駅前の門真プラザ再開発による超高層化計画に続き、大和田は駅前空間を大きく変える「広場整備基本構想」を門真市が2025年3月までにまとめ、5月1日に公表しました。
この広場構想は“銀行跡地の市有化をきっかけとした駅前の環境再整備”であり、古川橋や門真市駅前のように大きなビルを建てるわけでなく、狭すぎる駅前にひしめく建物(土地)を市有化したうえで公共の広場とし、快適にしましょうという内容です。
大和田は門真市内では一番重要といえる“バスターミナル(バスロータリー)”が古くから置かれていますが、駅前の空間も道路も狭すぎて、歩行者にも車にも快適とは言えない環境でした。

三菱UFJ銀行大和田支店の“統合”による店舗閉鎖を伝える告知文、大和田支店は古川橋駅前の門真支店と統合後、さらに守口支店に吸収され、現在は同店内で支店名と支店番号(230)だけが生きている(2022年5月)
そんななか、駅前のバス通り(守口門真線=府道158号)をはさんで真正面に建っていた銀行(三菱UFJ銀行大和田支店)が2020年10月に“店舗統合”という形で閉店。
この2200平方メートル超の土地を門真市が入手し、建物を解体したことで駅前空間がダイエーあたりまで一気にひらけることになり、大和田駅前の広場化計画が動き出しました。
対象エリアは、銀行跡と、道路をはさんだ駅側ではバスロータリーから「旧松屋大和田店(2022年9月閉店、現在は建物解体)」があった市道までの一画(約3150平方メートル)に加え、北口(常称寺町・宮野町・大阪国際大学側)のタクシー乗場・ロータリー(約1700平方メートル)も含まれました。
門真市、古川橋の次は当然……
大和田は、1970年代から90年代までの駅前再開発で広場が整備された門真市や古川橋とは異なり、重要なバス乗り換え駅で一時期は門真市内で最多の乗降客数さえあったのに、狭苦しい駅前環境が放置されてきた歴史がありました。
行政の“放置ぶり”では、となりの萱島(門真市側の西口のみ、寝屋川市側の東口は駅前広場を整備)もいい勝負ですが、ここは市境で駅の所在地が寝屋川市という事情を持ち、守口市境の西三荘は住所こそ門真市に入っていますが、1970年代に旧門真駅の代替かつ巨大企業本社の“門前駅”として設けられたという経緯もあります。両駅前とも新たなまちづくりが始まる気配は見られません。
そんな市境2駅を除いて、門真市、古川橋とくれば、次に再生に取り組むのは順序から見て大和田というのは必然ともいえます。
もともと京阪電車が1910(明治43)年に開通したとき、門真市内に設けられたのは「門真(現在の西三荘駅近くにあった旧門真駅)」と「古川橋」の2駅(路面電車区間の多かった当時は停留所的な駅)だけ。
当時の大和田村が四半世紀にわたって駅の設置を請願し、約1000坪(3300平方メートル超)の敷地を京阪電鉄に提供し、大和田駅(停留所)が設けられたのは開通から20年以上を経た1932(昭和7)年10月14日のことでした。
歴史的に見ても、大和田が門真や古川橋の次という扱いになるのは止むを得ないのかもしれません。
大和田駅前で最初の三和銀行
そして、広場構想の端緒となった旧三菱UFJ銀行の大和田支店についても市有化するしかなかった場所、ともいえます。
同銀行は「三和銀行大和田支店」として1964(昭和39)年9月に開店した大和田駅前ではもっとも古い都市銀行で、初期に進出しただけに駅真正面の敷地にも余裕があり、相応の広さを確保した平面駐車場も持っていました。
その後に進出した東海銀行(1969年12月開店)や第一勧業銀行(1974年6月開店)とともに、大和田駅前の“三大都市銀行”として、門真市内で1号店となる旧ダイエー大和田店(1969年開店、2001年閉店)とともに、1970年から90年代初頭にかけて賑やかな商店街をけん引していたのは懐かしい思い出です。
2002(平成14)年に三和銀行と東海銀行が合併して「UFJ銀行」となった際も、ダイエー至近にあった東海銀行のほうを暫定的に大和田南支店という名に変え、1年ほど存続させたうえで三和銀行大和田支店側が吸収し、次にやってきた東京三菱銀行との合併の波も乗り越え、5年前まで生き残ってきました。いわば、駅とともに大和田駅前を代表してきた民間施設の一つです。
市が土地・建物を買収する際に15億円以上を費やしたと言われ、高額ではないかとの指摘を受けていましたが、放っておけば民間企業が土地・高度いっぱいに建物を建て、駅前がさらに窮屈なものになっていた可能性もあります。
そして、大和田駅前で一番目立つ場所を市有地化しておくことで、古くなりつつある周辺の建物をどうするか、となった際に影響を与えるのではないでしょうか。
たとえば、第一勧業銀行の大和田支店として進出した隣接地(古川橋寄り)の建物は、合併で「みずほ銀行大和田支店」となり、支店統合という名の撤退後は、りそな系の関西アーバン銀行門真支店に変わり、現在は「関西みらい銀行門真支店」して使われています。
進出時期を考えても、建物は半世紀を経過したとみられ、第一勧銀時代に1階の出店的なスペースに「宝くじ」目当ての買物客が常に集まっていたことを遠い昔として思い出されるほど。
銀行のリアル店舗縮減の流れが続くなか、建て替えてまで店を残すのかどうか。そして同ビルの裏手には、80年代の街が賑やかだったころからおなじみのビルや建物も散見されます。
これらのビル・建物を建て替える際には、大和田駅前の“大地主”となった門真市が一定の影響力を持つことができるはずで、駅前のまちづくりをリードしていく役割が期待されます。
駅前での立ち退きは進むか
今回門真市が公表した大和田駅前の「広場整備基本構想」によると、
A.えきとまちが一体となった仕掛けづくり(周辺道路の改修、駅の南北広場を行き来しやすい導線)
B.安全で快適な交通結節点の整備(交通広場に隣接した快適な待合空間、横断歩道などの再編)
C.どんな場面でも人が集い、活躍する滞留空間の整備(芝生広場、大屋根、ベンチ、テーブル、遊具など)
D.公民連携による持続可能な監理運営体制の構築(市と自治会・町内会などの地域と連携した維持管理)
――という考え方で2025(令和7)年度以降(完成時期未定)に駅前広場を整備していくとしています。
一例として完成時のイメージイラストも公開されており、これを見ると大和田駅前(南口=バスロータリー側)の雰囲気を一気に変えるインパクトを持つ構想であることが分かります。
具体的なスケジュールはまだ決まっておらず、特に駅バスロータリー側には現在も民間の建物が建っていて、土地所有者が7人、建物所有者は10人いるとされています。市はこれらの人と交渉して立ち退いてもらい、土地を入手しない限り計画は進みません。
駅構内とバス乗場の間にある自転車預かり所など、長い間にわたって商売をしている店舗もみられ、すぐに理解を得られるかどうかは不透明です。
それまでの間、銀行跡地を“空地感”や“放置感”を出した未管理の広場として置いておくと、屋外飲酒場に使われてしまうなど、逆にイメージが悪化してしまうので対策も必要となるでしょう。
また、バス乗場と反対側の「北口」をどうするのかや、南口とどのように連携させていくかも考えなくてはなりません。南北出入口をつなぐ高架下の「エル大和田」などの商業施設も刷新したいところ。
一方、大和田駅の大きな特徴であるバス乗場ですが、門真団地や四条畷駅へ向かう京阪バスの主力路線であっても運転本数は減るばかりで、現時点で増える要素が見られません。
かつての“バスターミナル”的な施設よりも、タクシーやオンデマンド交通、または各種モビリティといった移動手段へもアクセスしやすい環境がより重要となります。
高齢化対策でもう一つ言えば、大和田駅の長いホームに停車する京阪電車の多くが4両の短い編成となってしまったので、車両の停まる位置まで上手くアクセスできるような導線も考えたいところです。
大和田駅の利用者が1990年初頭と比べて半分近く減っていたことは、3年前の記事「門真を走る『京阪電車』、大和田駅と古川橋駅の復活が大きな鍵」(2022年5月)に詳しく書きましたが、この先、大幅な人口増は見込めないまでも、駅前が快適に変わり、イベントなどで楽しくなっていけば、藤田(とうだ)町など駅に近い守口市域も含め、周辺地域での定住や移住促進の大きな力となるでしょう。
特に大和田駅は門真団地や巣本など市内南部へ向かう交通アクセスの玄関口でもあり、門真市民に与える影響は小さくないはずです。
(2025年5月13日時点の内容です)
(※)この記事は門真市公式サイト内に公開された「門真市大和田駅前広場整備基本構想」、門真市議会議事録などを参照しました